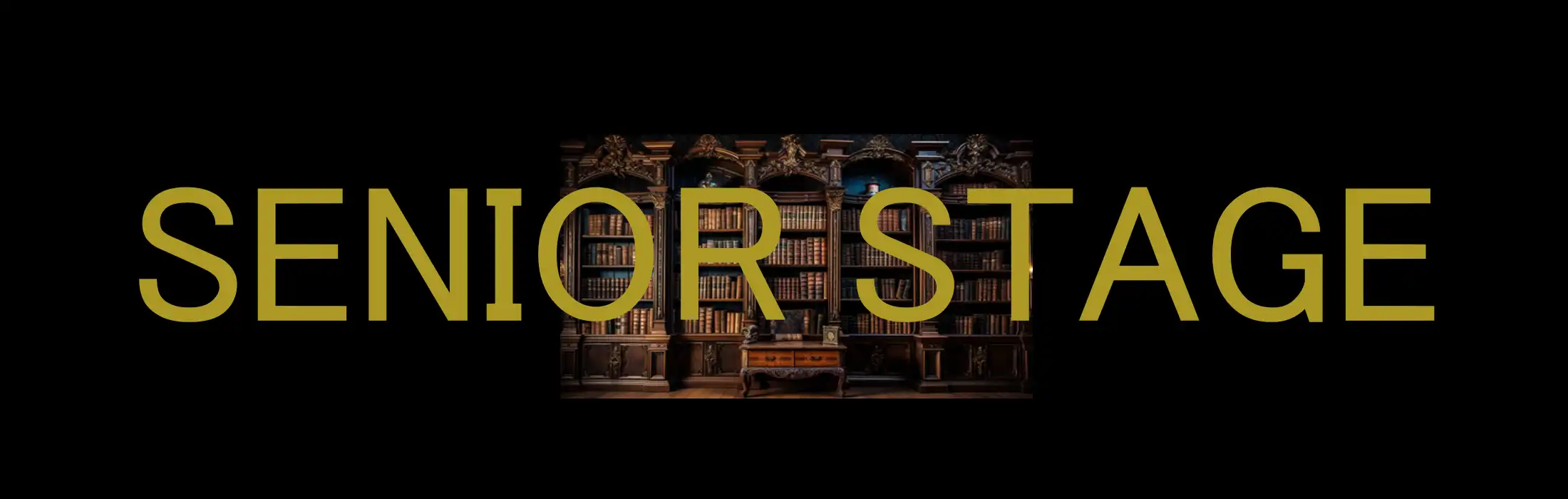ブログや記事を書くとき、多くの人がつまずくのは「書き出し」ではなく、実は記事構成の作り方です。
テーマは決まっているのに、見出しや流れを考えているうちに時間だけが過ぎてしまい、書き始める前に疲れてしまう…
私も以前は、この記事構成づくりに1〜2時間かかることが当たり前でした。
しかし、ChatGPT-5を活用するようになってから状況は一変。わずか5分で記事の骨格が完成し、そのまま本文執筆に移れるようになりました。
この記事では、初心者でもすぐ真似できるChatGPT-5で記事構成を作る具体的な方法と、短時間で完成度を上げる効率化のコツをご紹介します。
もし構成作りに時間を奪われているなら、今日からその悩みを解消する方法を一緒に見ていきましょう。
ChatGPT-5が記事構成作りを時短できる3つの理由

文脈理解力の向上
ChatGPT-5は、以前のモデルに比べて文章全体の流れをつかむのがとても得意になりました。
単語の意味だけでなく、前後のつながりや背景も踏まえて考えてくれるので、指示の意図から外れにくいのです。
そのおかげで、テーマに合った一貫性のある見出し構成をスムーズに作れるようになりました。
複雑な指示にも正確に対応
「テーマはこれで、読者はこういう人で、文字数はこのくらい、見出しはH2とH3で…」といった細かい条件も、しっかり受け止めて反映してくれます。
複数の条件をまとめて出しても情報が抜けたり順番が変になったりしにくいので、最初から完成度の高い骨格が手に入ります。
結果的に、頭の中で迷う時間をほとんどゼロにできて、すぐ書き始められます。
ストーリー性のある構成生成
ただ情報を並べるだけではなく、読み手が自然に流れを追えるように見出しを並べてくれるのも大きな魅力です。
導入から結論までスッと読めるストーリーができあがるので、最後まで読み切ってもらいやすくなります。
特にブログや記事では、読者の滞在時間や満足感アップにもつながります。
ChatGPT-5で記事の骨格を作る3ステップ

記事の目的とターゲットを明確にする
まずはAIに投げる前に、次の3点を整理します。
- 読者像(誰に向けて書くのか)
- テーマの軸(何を中心に伝えるのか)
- 行動目標(読者にどう動いてほしいのか)
例:
ブログ初心者に向けて、ChatGPT-5を使って5分で記事構成を作る方法を伝える。
ChatGPT-5に的確なプロンプトを与える方法
プロンプトはできるだけ具体的に書くことが大切です。
以下は実際に使える例です。
あなたはプロの編集者です。
以下の条件で記事構成を作ってください。
- テーマ:「ChatGPT-5で記事構成を5分で作る方法」
- 読者:ライターやブロガー初心者
- 文字数:3,000文字前後
- 見出しはH2とH3を使用
- PREP法を意識
- 実例と応用方法も入れる
出力された構成を自分仕様に微調整する
AIが作った骨格は優秀ですが、そのままだと「あなたらしさ」が足りません。
自分の経験談や失敗談を入れる余地を残すことで、読み応えと説得力が増します。
チェックすべきポイントは次の3つです。
- 見出しの順序は自然か
- 重要な部分が埋もれていないか
- 事例や体験談を差し込む場所があるか
ChatGPT-5構成作成の実例と他ジャンルへの応用
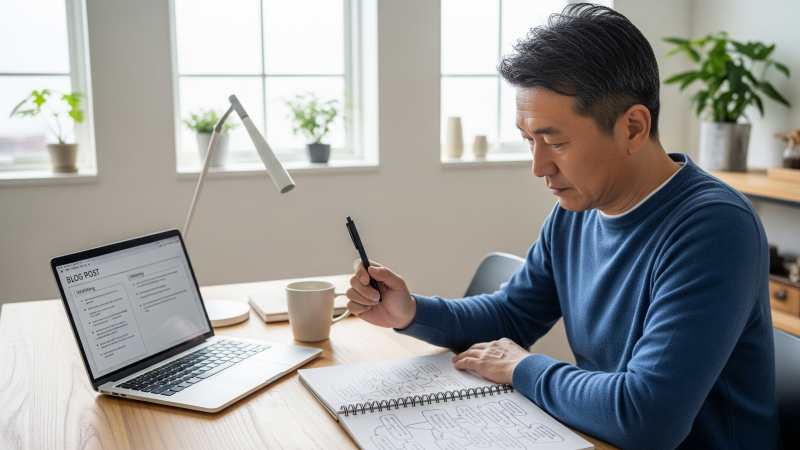
実際に生成した構成サンプル
先ほどご紹介した「テーマ・読者・文字数・見出し形式」などを細かく指定したプロンプトをChatGPT-5に入力すると、こんな構成案が返ってきます。
- H2: はじめに
- H2: ChatGPT-5で骨格作りが早くなる理由
- H2: 5分で骨格を作る手順(H3ごとの工程付き)
- H2: 実例と応用例
- H2: 効率化のコツ
- H2: まとめ
このように、見出しの順序や内容もきちんと整理されているので、そのまま本文を書き進める土台として使えます。
ブログ以外(YouTube台本、メルマガ、電子書籍)での活用例
- YouTube台本:導入→本編→まとめを先に決めて撮影効率をアップ。
- メルマガ:読者の反応を想定したストーリー展開がしやすくなる。
- 電子書籍:章立てをAIに作らせてから肉付けすれば、短期間で原稿を仕上げやすい。
ChatGPT-5で記事構成を作るときの効率化のコツ

条件指定を細かく設定する
「何文字で」「誰向けに」「どんな形式で」まで、できるだけ具体的に指定しましょう。
例えば「3,000文字で、ブログ初心者向けに、見出しはH2とH3で」などと細かく条件を出すと、AIはその通りの構成を作ってくれます。
あいまいな依頼だと方向性がブレたり、必要な要素が抜け落ちたりすることがありますが、明確な条件を与えれば出力の質が安定し、最初から完成度の高い骨格が手に入ります。
見出し形式(H2/H3)を統一する
見出しの形式を統一することで、記事全体の構造が整い、読者にとって読みやすくなります。
例えば、H2は大見出し、H3はその補足や詳細というように役割を決めておくと、内容の階層が明確になり、情報が頭に入りやすくなります。
さらに、検索エンジンにとっても記事の構造が理解しやすくなるため、SEOの評価も安定します。
できればサイト全体でルールを統一するのが理想です。
体験談や事例を組み込む
読者は、リアルな体験や具体的な事例に強く反応します。
AIが作った骨格は効率的ですが、無機質になりがちです。そこにあなた自身の経験やエピソードを重ねることで、文章に温かみや説得力が生まれます。
例えば「私が初めてChatGPT-5で構成を作ったときは…」という形で始めると、読み手は自然と続きを知りたくなります。
こうした人間らしい要素が加わることで、記憶に残る記事になります。
まとめ|ChatGPT-5で構成作りを時短して執筆に集中しよう
- 記事構成は、書きやすさと完成度を左右する重要な工程
- ChatGPT-5は文脈理解や複雑な指示対応に優れ、短時間で骨格を作れる
- 「文字数・読者・形式」など条件を細かく指定することで出力の精度が安定
- 見出し形式を統一し、体験談や事例を加えると読みやすく記憶に残る記事に
- 5分で骨格を作り、執筆時間を大幅に短縮できる
記事構成は、執筆の質とスピードを決める大事な工程です。
ChatGPT-5なら、この工程を5分で終わらせ、すぐに本文作成へ進めます。
今日からぜひ試して、構成作りのストレスを減らしていきましょう。